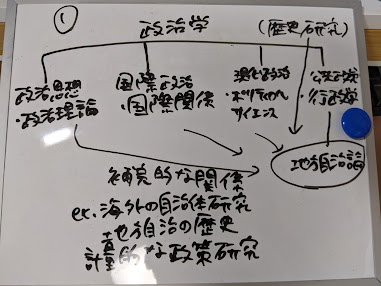第2回「CHAPTER1:首長」
■事前準備 テキスト第1章本文(pp.2~20)を読んできてください 講義は10月1日21時30分から開始予定です ■レジュメ 1.首長に関する制度 〇権限の比較 ・制限列挙方式:法律で示されている具体的な権限しか行使できない(議会の権限) ・概括例示方式:「このような権限がある」と解釈可能(首長の権限) 〇影響力の比較 ・自治体職員に対する影響力 →首長部局、行政委員会の存在 ・議会に対する影響力 →専権事項、議案提出権、再議請求権 ・住民に対する影響力 →徴税、土地収用、条例制定、避難命令 〇首長の影響力まとめ ・強力で、広範 →誰が首長になるかによって自治体の在り方が変わる ・住民、議員、自治体職員によって受ける影響は異なる 2.首長の実像 〇日常活動 ・行政官としての活動 ・再選を目指す政治家としての活動 〇首長の前職 ◇知事の場合 ・知事は中央省庁出身者が最多 →総務省出身が多い →総務省職員は自治体幹部としての出向を通じてキャリアを形成する →逆に自治体職員出身者は少なくなっている ・なぜ中央省庁出身者が多いか? →中央政府の意向? ◇市長の場合 ・かつては市職員出身者が多数 ・現代は都道府県議会出身者が増加 →地方分権改革の影響(都道府県議会議員にとって、市長ポストの魅力が増した) →選挙制度改革の影響(国政進出を断念し、市長へと変更する要因に) →議員年金廃止の影響 →平成の大合併の影響 3.首長の給与・待遇 〇給与削減の流れ ・財政改革の一環として ・給与の低さが首長の魅力を減らしている? →首長の給与をカットしても財政に影響はない 4.首長の退任 〇任期満了による退任 ・任期は4年(地方自治法) ・再選の制限はない ・任期満了での退任は引退か落選のどちらか 〇任期途中での退任 ・多いのは健康事情(死亡、病気)など ・他の公選職への立候補 →辞職後に国政選挙や知事選挙に出るパターン ・いずれにせよ、政治的な対立よりも個人的な理由が多い →近年ではリコールや不信任決議をきっかけに辞職する例も出てきている コラム1「地方政治におけるポピュリズム」 〇地方政治におけるポピュリズムの評価 ・既存の地方行政や地方政治に対する不満の表れ →イギリスやアメリカでも同じような不満の表出は観測される ・対立する相手への批判が先鋭化し、拡大する →過剰な批...